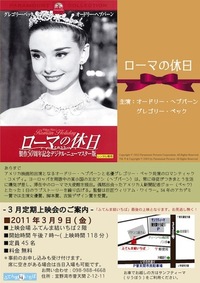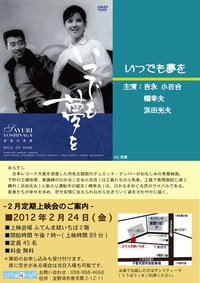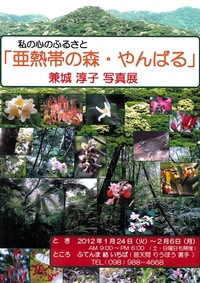2010年05月10日
普天間から発展した宜野湾

2000年宜野湾市
戦後の普天間の歴史について紹介したいと思います

宜野湾市の経済の発展は普天間から始まりました。
でも、その発展の影には
戦争によって建物が壊滅的になくなってしまったことで
生きていく為に基地に依存することで生活の基盤を立て直していった現状と、
27年にも及ぶアメリカ軍統治下の中での混乱から
大きな民衆運動へと広がり、その後日本復帰へと
時代の流れに大きく翻弄された人々の苦悩がありました。
1945年
沖縄戦で死亡した宜野湾村民は、3,674名。
死亡率は当時の人口13,636人の約3割に達する。
1946年
宜野湾村人口6,094名と報告
戦後、米軍は日本本土戦略の為、
沖縄を徹底して軍事基地化する方針を打ち出し、基地の周辺から人々を立ち退かせました。
戦場を生き残った宜野湾村民は、野嵩や島袋(北中城)に設置された民間収容所へと収容され
「戦後の生活」をスタートさせていきました。
野嵩の収容所は「中継地点」として、人の移動が頻繁に行われていたそうです。
野嵩やその周辺地域で生活する村民は、
米軍の許可が下がり次第、元のふるさとへ帰っていきました。
しかし、ふるさとにはかつての面影はなく、人々は基地を取り囲むようにして家を建て、
新たな生活をスタートさせました。
1950年7月の時点で、宜野湾村の約50%以上が軍用地。
宜野湾はいびつな復興をたどっていくことになります。
1946年 軍政府の主導の「政治復興」により戦前の市町村が復活。
1945〜1948年デイリーオキナワン
デイリーオキナワンは普天間に社を構えたアメリカ軍人・軍属向けの新聞社でした。
デイリーでは、アメリカ人以外にもフィリピン人や社の周囲で生活する
沖縄の人々が働いていました。
1946〜1949年 AJカンパン
普天間にはアトキンソン・ジョーンズ社というアメリカの会社の従業員住み込み宿舎があり
この会社は基地建設を請け負いました。
AJカンパンには他市町村出身者が多く住み込み、
多い時には3,000人もの人々が働いていました。
1950年〜1953年 朝鮮戦争
中華人民共和国成立、朝鮮戦争を契機に「太平洋の要石」として位置付けられる。
1962年 宜野湾村から宜野湾市へ昇格(人口3万人を超えた)
普天間は建設ブーム年間400軒以上の店舗や住宅が立ち、基地に働く労働人口も増加。
1962〜1979年 普天間の沖縄食糧跡地に公設市場開設。


使用料は一坪あたり、1日8セント〜10セントであった。

宜野湾の中心市街地として発展。
1965年〜1975年 ベトナム戦争
1972年5月15日 沖縄本土復帰
日米両国が締結した安全保障条約によって
日本本土の米軍基地は4分の1に減少したが、逆に
沖縄の米軍基地は2倍に増加した。
普天間飛行場は海兵隊専用基地として整備強化され、現在に至っている。
1996年 普天間基地返還、日米合意。
現在の宜野湾市について
・人口 92,813名(2010年3月)
・農業 田いも *農業を仕事としている人たちの数は年々減ってきている。
・商工業 宜野湾市には1,000を超えるお店などがあり、
7,000を超える人がそこで働いている。
特に、近年の西海岸地域の発展はいちじるしく、
この地域の発展は、雇用の場の創出につながる。
その一方で、昔からの商業地として形成されている
普天間の中心市街地などは、衰退の傾向にあり、街の中心として
賑わいを取り戻すことが望まれています。
・工業 約90の事業所、食料品をつくっている所は20箇所
・基地 約25%が基地
普天間飛行場の大部分が民有地
地権者は約2.900名
軍人軍属が約3.700名 約200名の日本人従業員。
*現在の普天間*
米軍から解放された跡に、自然発生的に都市計画がないままに出来たことから
駐車場の未整備や、道路幅員が狭く近代的な商店街が形成されず、
消費者ニーズに合わなかったことで年々衰退する状況にある。
*普天間歴史のこぼれ話*
宜野湾村が市に昇格する際に、市の名称を何にするかで、議論になったそうです。
宜野湾の心臓部である普天間の名称を取って市名を普天間市にすべきであるという意見と、
宜野湾市にすべきという二つの意見があって、最終的には票決で宜野湾市となったようです。
いやぁ〜もしかすると普天間市になっていたかもしれないんですね。
最近は、これまでにないぐらいの報道で
普天間は知名度を上げていますが、
これからの普天間の街をどうしていくのか
真剣に考えていく時期にきています。
戦前の普天間についてはこちら↓
http://futima1.ti-da.net/e2833398.html
Posted by エリカ様 at 17:46│Comments(0)
│ふてんまの歴史